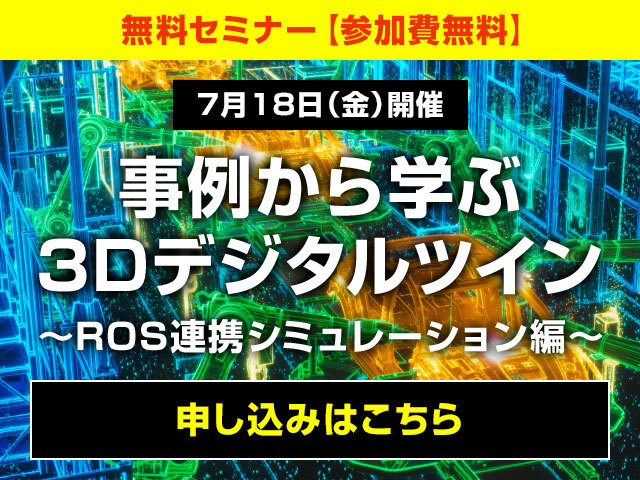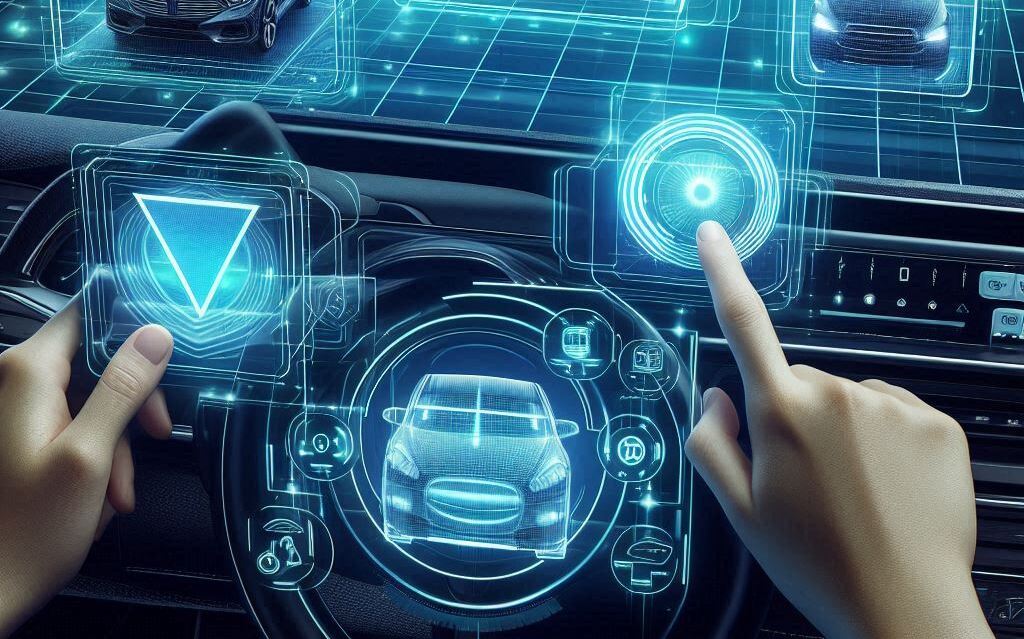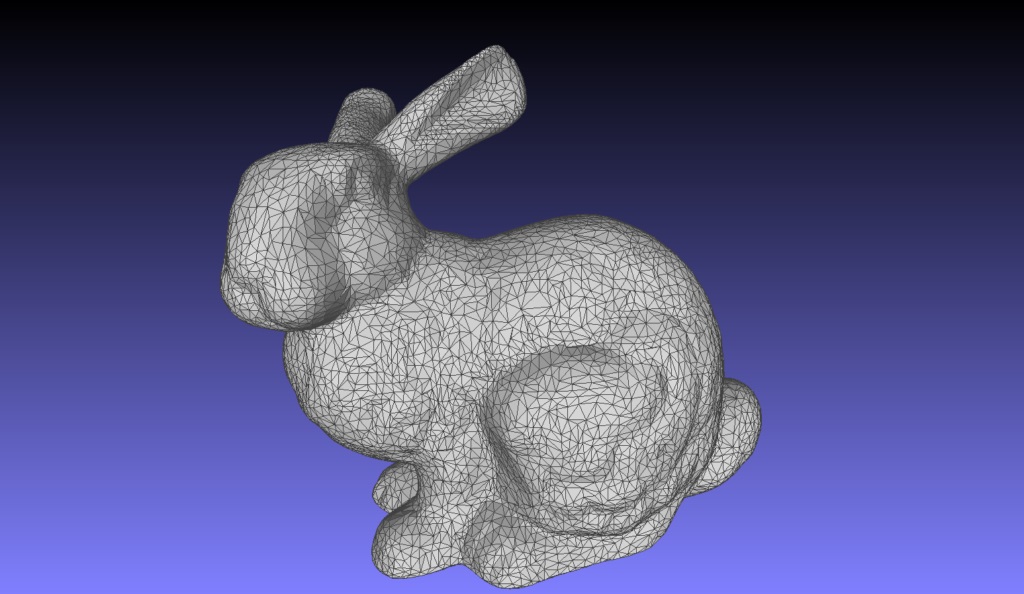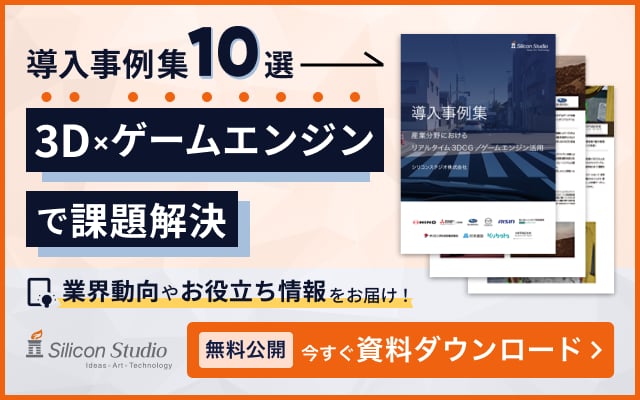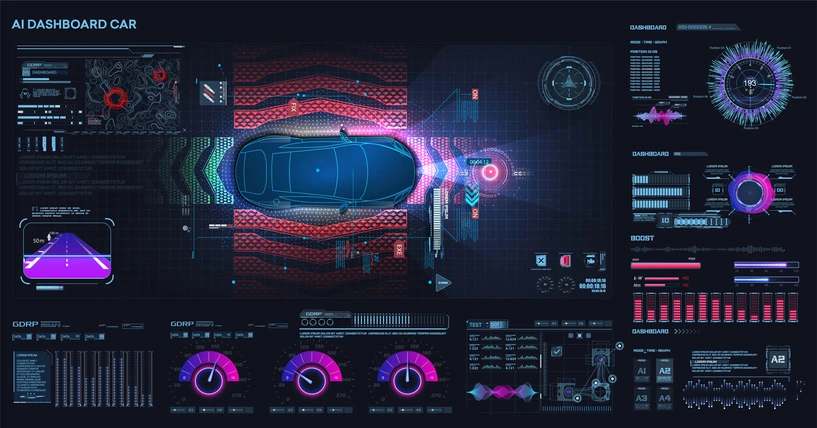
- 自動車・モビリティ
2025.02.12
SDVとは?次世代自動車に期待されている成果と課題
自動車業界は、技術革新や環境規制の強化、消費者ニーズの変化などにより大きな転換期を迎えています。
業界は新たな価値創造に向けて動き出していますが、その中心と言える重要なイノベーションが、ソフトウェアで車両の機能や性能を定義するSDV (Software Defined Vehicle) です。
SDVは自動車の未来を変える可能性を秘めていますが、その実現には多くの課題も存在します。
本記事では、SDVについて期待される成果と課題をご紹介します。
SDVの定義と概念
SDV(Software Defined Vehicle)は、ソフトウェアを変更することで価値や機能がアップデートされることを前提に設計・開発された自動車・モビリティのことです。
具体的には、クラウドとの通信により自動車の機能を継続的にアップデートすることで、運転機能の高度化など新たな価値の実現が可能となる次世代の自動車・モビリティを指します。CASEの各要素を統合し、より高度な自動車システムを実現するための重要な技術基盤です。
2024年5月に経済産業省と国土交通省が策定した「モビリティDX戦略」においても、SDVは電動化と並ぶ競争基軸として捉えられており、その重要性が強調されています。
SDVの開発は、従来のハードウェア中心の車両設計から、ソフトウェア主導の設計へと移行するアプローチです。
ビークルOSやAPIの標準化により、ハードウェアとソフトウェアの分離(ディカップリング)が進み、柔軟な開発が可能になります。
SDVは自動車産業に革命をもたらす可能性があり、今後の技術開発や業界動向に大きな影響を与えると期待されています。
【コラム】自動車・モビリティ業界は大変革期!CASEの理解がカギを握る
SDVのメリットと期待される成果
SDVを実現することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。
ここでは、SDVのメリットと期待される成果についてご紹介します。
OTAによる車両の機能追加と価値向上
無線通信を経由したデータの送受信によりソフトウェアを更新するOTA(Over The Air)は、SDVの重要な要素技術の1つです。
この技術により、購入後もハードウェアをアップデートすることなく新機能を追加したり、性能の強化や問題解決をしたりすることで、車の価値が向上します。
また、ユーザーは自分好みのアプリやエンターテインメント機能を追加し、車をカスタマイズすることも可能です。
カーシェアリングの普及にともない、重要な機能となる可能性があるでしょう。
自動車メーカーにとっては、ソフトウェア更新やアプリ販売を通じて、車両販売後も継続的に収益を得られる新たなビジネスモデルの構築につながります。
クラウドとの通信による機能の継続的なアップデートと運転機能の高度化
SDVは、クラウド通信を活用して車両機能を継続的にアップデートし、運転機能を高度化する次世代自動車です。
OTAによる迅速なセキュリティ修正や自動運転技術の段階的進化が可能となり、エンターテインメントだけでなく、本質的な運転機能の更新も実現します。
ただし、ハードウェアの制約内での改善が中心となるため、安全性確保や開発管理などの課題は存在します。
ソフトウェアとハードウェアの分離、ビークルOSと標準化されたAPIの開発など技術的課題の克服が必要ですが、これらを解決することで自動車産業に新たな価値創造の機会をもたらすでしょう。
SDVの技術面の課題と解決策
SDVの実現に向けては、以下のような課題があります。
- ハードウェアとソフトウェアの分離
- ビークルOSと標準化されたAPIの開発
- ITインフラ、データ管理、コネクティビティ、E/Eアーキテクチャの強化
これらの課題に対する解決策を検討することが、SDVの成功には不可欠です。
それぞれの内容を少し詳しく確認しておきましょう。
ハードウェアとソフトウェアの分離

ハードウェアとソフトウェアの分離は、SDVの実現における重要課題です。
従来は両者が密接に結びついていましたが、SDVではソフトウェアを独立して開発し、効率化や柔軟性向上、コスト削減を図ります。
その結果、迅速な開発やソフトウェアの再利用が可能になりますが、自動車業界では安全性のため緊密な連携が求められる場面もあり、完全な分離には技術的課題が伴います。
ハードウェアとソフトウェアの分離を実現するためには、ハードウェアの違いを吸収して同じソフトウェアでも異なるハードウェアを制御するためのビークルOSと、インターフェースとしての標準化されたAPIが不可欠です。
さらにテロジニアスCPU構成、高度なスケジューリング、メモリ分離、大規模SoC(System-on-Chip)といった技術を組み合わせることで、柔軟なシステム構成と高い安全性を確保することが可能になります。
ビークルOSと標準化されたAPIの開発
ハードウェアとソフトウェアの分離を実現するために不可欠なビークルOSと標準化されたAPIは、ハードウェア資源の抽象化、ソフトウェア互換性の確保、OTAアップデートを可能にします。
異なる車両のハードウェアを統一APIで抽象化し、ソフトウェアの効率的開発や遠隔更新、機能拡張を実現できることがメリットです。
しかし、開発や標準化には課題が多く、業界全体での協力が求められます。
ビークルOSの開発では、車両のハードウェア資源を適切に抽象化し、一つのソフトウェアで複数の種類の車両を制御できるようにすることは容易ではありません。また、車両のどの部分を、どの階層で、どのように抽象化するかを決定する必要があります。さらに複数のアプリケーションによる制御の調停や、車両の安全性をビークルOSで担保することが必要です。
標準化されたAPIの開発では、自動車メーカーを超えた標準化の必要性について議論が分かれています。また、APIをどの階層で定義するかは、自動車業界のビジネスモデルに大きく影響します。
また、APIの標準化だけでは十分な互換性を確保することが困難で、さらにボディー系に限らず、AD/ADASを含むすべてのドメインのAPI策定に取り組む必要があります。
これらの課題に対処するために、2024年6月20日には名古屋大学によってOpen SDV Initiativeが設立されました。産業界と学術界が協力してSDVの実現に向けた標準化と技術開発が進められているところです。
ITインフラ、データ管理、コネクティビティ、E/Eアーキテクチャの強化
SDVの実現にはIT技術の強化が不可欠です。
膨大な量のデータ管理が必要となり、2022年にはコネクテッドカーのデータ量が20エクサバイトに達し、2027年には117エクサバイトに達すると推定されています。
この急増するデータ量に対応するため、強力なITインフラと効率的なデータ処理・管理システム、高速通信技術(5Gなど)、セキュアな通信プロトコルが求められます。
また、E/Eアーキテクチャ(Electrical/Electronicアーキテクチャ)強化のため、中央集権型システムや高性能コンピューティングユニット(HPC)の導入も必要です。
従来の分散型アーキテクチャからドメイン型およびゾーン型アーキテクチャへの移行が進んでいます。これにより、ECU(電子制御ユニット)の数を大幅に削減し、高性能ドメインコンピュータに集約することが可能です。
自動運転技術の進化やリアルタイムの車両モニタリング、高度なインフォテインメントシステムの実現が期待されます。
SDVによるビジネス面への影響と戦略
SDVの発展により、自動車業界のビジネスは大きな変革を迎えるでしょう。
ここでは、SDVによるビジネス面への影響と戦略を紹介します。
新たな収益構造とアプリ/サービス販売の展開
SDVの進化にともない、自動車メーカーの収益構造は大きく変化しています。
従来の車両販売による一時的な収益から、継続的な収益を生み出すモデルへと転換が進んでいる状況です。
OTAアップデートによる機能追加や性能向上、ソフトウェアの更新やカスタマイズサービス、スマートフォンのようなアプリストアの概念の導入、そして車両から収集されるデータを活用したアプリケーションやサービスなど、新たな収益源が生まれています。月額課金のようなサブスクリプションモデルも新たなビジネスモデルとして登場しています。
その結果、自動車メーカーは車両のライフサイクル全体を通じて継続的な収益を得ることが可能となり、ビジネスの安定性と成長性の向上が期待できるでしょう。
自動車メーカーやサプライヤーは、ソフトウェア開発能力の強化のほか、データ分析技術の向上や新たなパートナーシップの構築、顧客ニーズに合わせた柔軟なサービス提供体制の確立が重要な戦略となります。
サイバーセキュリティと半導体技術の重要性
![]()
SDVの発展により、サイバーセキュリティと半導体技術の重要性が飛躍的に高まっています。
コネクテッドカーの普及によりサイバー攻撃のリスクが増大し、車両システムの保護、個人情報の保護、OTAアップデートの安全性確保など、多層的なセキュリティ対策が必要です。
また、SDVの高度な機能を実現するため、高性能な半導体チップが不可欠となっており、自動運転、AI処理、高速データ通信などに対応する車載用半導体の性能と機能が急速に進化しています。
半導体の安定供給と技術革新は、SDVの発展と競争力を左右する重要な要素といえるでしょう。
日本の自動車産業の強みと課題 – 「Small is beautiful」「Safe is beautiful」「Smart is beautiful」
日本の自動車産業は、SDVの時代においても独自の強みを持っています。
伊藤忠総研の深尾三四郎主任研究員が提唱する「3つのS」は、日本の強みを象徴しています。省資源の小型・軽EVと交換式バッテリーへの国際的ニーズ、安全性に対する高い技術力と信頼性、そして電池健康状態データのマネジメント強化など、日本の技術力が活かせる分野が存在します。
しかし「自動車のスマホ化」に象徴される大変革に対して、日本企業は出遅れている面もあります。
AI、コネクテッド技術、ソフトウェア開発力などの分野で、米国や中国企業との差が開いていることが課題です。
日本の自動車産業が今後も競争力を維持するためには、これらの強みを活かしつつ、SDVやAI技術の分野での遅れを取り戻す努力が必要です。
SDVによる産業への影響と将来展望
SDVは、自動車産業に大きな変革をもたらし、その影響は広範囲に及ぶと予想されています。
ソフトウェアを中心とした車両開発により、自動車の機能や価値が大きく変わり、産業構造にも変化が生じる可能性もあるでしょう。
ここでは、SDVによる産業への影響と将来展望をご紹介します。
国内外でのSDVの目標とシェア(2030年、2035年の目標値)
日本政府は、SDVの普及に向けて具体的な目標を設定しています。
経済産業省と国土交通省が発表した『モビリティDX戦略』における目標は、以下のとおりです。
- 2030年:SDVのグローバル販売台数における日系シェア3割(約1100万台〜1200万台)
- 2035年: SDVのグローバル販売台数における日系シェア3割(約1700万台〜1900万台)
日産、ホンダ、スズキなどのメーカーが取り組む次世代SDVプラットフォームに関する共同研究契約
日本の自動車メーカーは、SDV開発に向けて協力体制を強化しています。
日産、ホンダ、スズキ、ダイハツが次世代SDVプラットフォームの共同研究契約を締結し、共通ソフトウェアプラットフォームの開発を進めている状況です。
各社の取り組みにより、開発コストの削減と効率化が期待され、各社の強みを活かした差別化も可能になるでしょう。
2025年以降の量産車への搭載を目指すこの共同研究は、SDV市場での日本メーカーの競争力確保に重要な意味を持ち、日本の自動車産業全体の競争力強化につながると期待されています。
SDVがもたらす新たな価値とユーザー体験
SDVは、自動車産業に革新をもたらす可能性があります。
OTA技術による継続的な機能アップデートにより、車の価値が時間とともに向上し、ユーザーは個人化された体験を得られるでしょう。
自動車メーカーにとっては、ソフトウェア更新やアプリ販売による新たな収益モデルが生まれます。
また、高度な運転支援や自動運転機能の実現、車両の長寿命化、さらには車両データを活用した新サービスの創出も期待されるでしょう。
技術的・ビジネス的な課題はありますが、SDVは自動車産業に大きな変革をもたらし、ユーザーに新たな価値を提供する可能性があります。
SDVの推進が国際競争力を強化する鍵となる
SDVは、ソフトウェア主導で機能向上や価値創出を実現する次世代自動車です。
OTA技術で購入後も機能更新が可能となり、カスタマイズ性や継続的収益モデルの構築が期待されています。
一方で、ハードウェアとソフトウェアの分離、ビークルOS開発、ITインフラ強化など技術的課題もあります。
日本は3つのSを強みに国際競争力を高める必要があり、SDVは産業構造を変革し、持続的な成長と新たなユーザー体験を提供することができるでしょう。
シリコンスタジオでは、ゲームエンジンおよび3Dグラフィックス関連技術でSDVを実現するためのモビリティDXを支援しております。
エンターテインメントコンテンツやインタラクティブな車載インフォテインメントの開発をはじめ、センサーフュージョンによる外界センシング精度向上や自動運転の学習・検証のためのシミュレーション環境など、さまざまな分野に対応します。
ぜひ、シリコンスタジオにご相談ください。
関連ページ:シリコンスタジオ「自動車・モビリティ業界向け製品・ソリューション」
■著者プロフィール:シリコンスタジオ編集部
自社開発による数々のミドルウェアを有し、CGの黎明期から今日に至るまでCG関連事業に取り組み、技術力(Technology)、表現力(Art)、発想力(Ideas)の研鑽を積み重ねてきたスペシャリスト集団。これら3つの力を高い次元で融合させ、CGが持つ可能性を最大限に発揮させられることを強みとしている。
DXコラムは、デジタルツインやメタバース、AIをはじめ産業界においてトレンドとなっているDX関連を中心としたさまざまなテーマを取り上げることにより、デジタル技術で業務の効率化を図ろうとする方々にとって役立つ学びや気付き、ノウハウなどを提供するキュレーション(情報まとめ)サイトです。