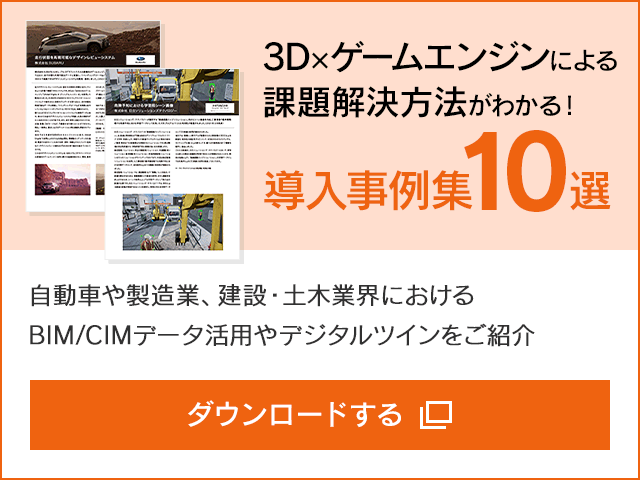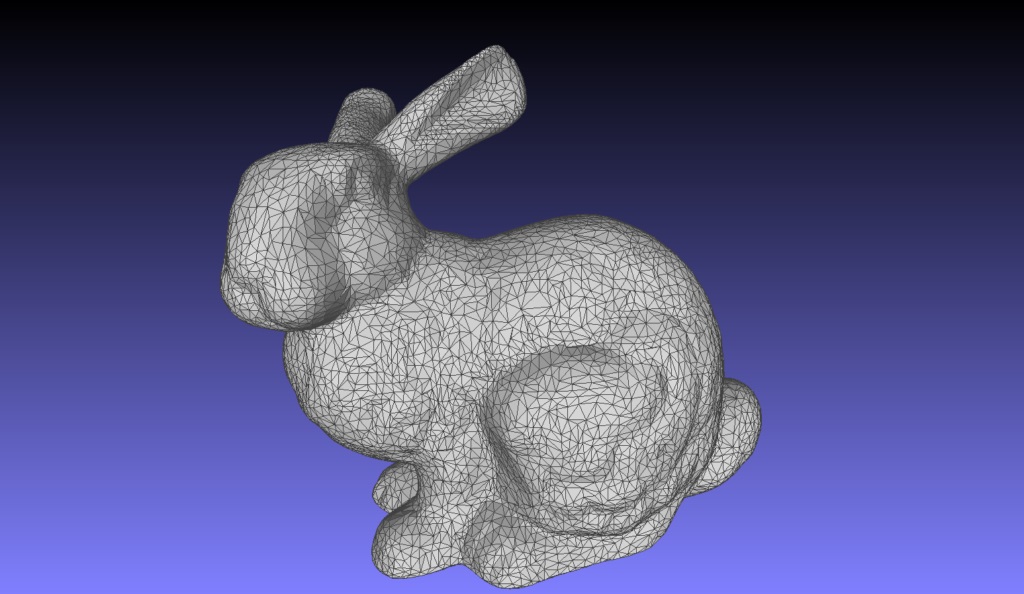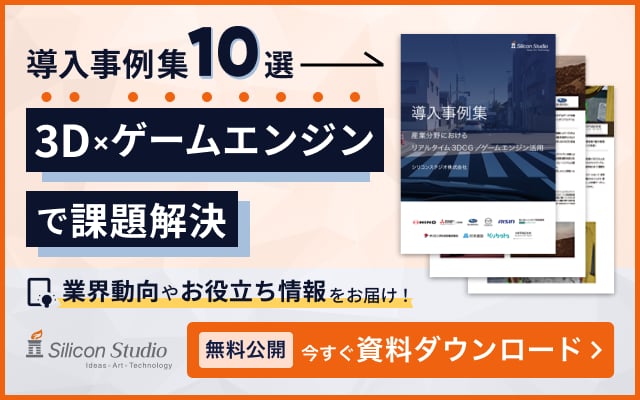- 自動車・モビリティ
2025.09.02
HMIの進化と3Dグラフィックス:情報から体験へ
- 目次
- この記事を読むのにかかる時間:6分
近年、自動車のHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)は、自動運転技術(AD)や運転支援機能(ADAS)の進化とともに単なる情報表示の役割を超え、ユーザー体験そのものをデザインする方向へと発展しています。車両が一部または多くの運転タスクを担うようになることで、ドライバーが「操作に集中する時間」から「体験を享受する時間」へと時間の質が変化しつつある状況です。
このような文脈において、HMIは「正しく情報を伝える」から「快適に、直感的に、豊かに伝える」へと役割を拡張しています。その変化を視覚面から支える重要な手段となっているのが3Dグラフィックス技術です。いまや3Dグラフィックスを活用した3D HMIの実装は、クルマの価値そのものを左右する要素となりつつあります。
本記事では、各国の先進自動車メーカーによる3D HMIの事例を通して、その現在と未来を見ていきます。
HMIとは:人とクルマをつなぐインターフェース

HMIとは、人と機械の間で情報をやり取りするための仕組みです。
自動車においては、メーター表示やタッチスクリーン、音声操作などを通じて、ドライバーとクルマが双方向に情報を伝え合う役割を果たします。
従来はメーター表示やスイッチ操作が中心でしたが、近年ではディスプレイの大型化や高精細化、タッチ操作、音声認識、視線検知などの技術進化により、情報の提示方法や操作性が大きく向上しています。
特にリアルタイム3Dグラフィックスの活用により、HMIはより直感的で没入感のある体験を提供する次世代のユーザーインターフェースへと変貌を遂げつつあります。
トヨタ自動車:安全性を両立する次世代HMI
トヨタ自動車は、HMIの進化において「現実解を重視する実用主義」と、「将来を見据えたUX設計」のバランスを取りながら開発を進めており、トヨタおよびレクサスでは、次世代HMIの開発にリアルタイム3D技術を積極的に採用しています。
「安心・安全」を最優先としつつ、それを支える形での「エンターテインメント性」の導入を目指しているUX設計が特徴的です。これは、トヨタが推進するSDV構想における「安心安全を提供できるHMI」「運転に集中できるコックピット」による「事故ゼロ」へのアプローチの一環となっています。
単なる表現技術の進化にとどまらず、安全と垣根のない開発協働体制の基盤としても機能しています。
※SDVについては、別のコラムで詳しく解説しています。
マツダ:フルディスプレイメーターで体験と視認性を高める
マツダのSUVシリーズ、CX‑60、CX‑70、CX‑90では、パナソニック オートモーティブシステムズ製の12.3インチフルディスプレイメーターが採用されており、3Dグラフィックスによる立体的な奥行き表現で高級感と視認性の向上を実現しています。
ドライブモードに応じた画面切替や周囲の状況をリアルに表示することで、安全運転支援の役割を果たすとともに、運転体験の質を高めています。
このように、マツダの3D HMIは視覚的な質感と安心感の両立を目指した実用的な応用例と言えます。
なお、マツダは人間中心の自動運転コンセプト「MAZDA CO-PILOT CONCEPT(マツダ・コ・パイロット・コンセプト)」に基づき開発を進めています。
シリコンスタジオでは、環境認識・認知領域における深層学習アルゴリズム検証用教師データ作成を支援すべく、MAZDA CO-PILOT CONCEPT技術開発用合成データ生成・編集ツールを開発・提供しました。
詳しい内容は導入事例で紹介しています。
BMW:Panoramic Visionと次世代HUDに見る3D情報設計
出典:BMW「The first-ever BMW Panoramic iDrive」
BMWは、HMIの未来を「視線の延長線上」に見据えています。
2023年に公開された「BMW Panoramic Vision」は、従来のHUD(ヘッドアップディスプレイ)を大きく進化させたものです。フロントウィンドウ全体に情報を3Dで投影することで、運転中の視線移動を最小限に抑えつつ、直感的な情報認知を可能にしています。
このPanoramic Visionでは、ドライバーと助手席の乗員の視点に応じて情報がレイヤー状に表示される構造となっており、必要な情報が立体的に浮かび上がるように見えるのが特徴です。
たとえば、スピード表示やナビの矢印、ドライバーアシスト情報が奥行きをもって表示されることで、視認性が高まっています。
さらに「CES2025」では、Panoramic Visionディスプレイが組み合わされた次世代の最新HMI「iDrive 9」が発表されました。
3D表現が積極的に使われおり、ジェスチャー操作や視線検知技術との組み合わせで、より自然な情報操作と没入感ある体験を提供しています。
Mercedes-Benz:MBUXと没入型デジタルコックピット

Mercedes-Benzが展開する「MBUX(Mercedes-Benz User Experience)」は、3Dグラフィックスを活用したHMIの先駆的な存在として知られています。
とくに2021年に登場したMBUX Hyperscreenは、車内のダッシュボードを覆う巨大なカーブディスプレイが特徴で、まるでガラスの中に情報が浮かんでいるような近未来的な印象を与えます。
このシステムでは、リアルタイムの3Dレンダリングを用いて、地図、車両状態、エンターテインメントなどを滑らかに表示。情報が立体的かつ動的に表示されることで、ユーザーはまるで画面に「触れているような感覚」で操作が可能です。
また、Mercedes-Benzは視線追跡や空間音響との連携によって、視覚・聴覚・触覚の感覚統合型HMIを目指しています。
MBUXは、3Dグラフィックス技術をベースに単なる映像表現を超えて、人の感覚に働きかけるインターフェースとして進化している代表例です。
XPeng Motors:G9とIM L7に見る中国EVの3D HMI戦略
中国のEVメーカーにおいても、3Dグラフィックスを活用したHMIの革新が急速に進んでいます。XPeng Motorsの「G9」や、IM Motorsの「L7」などは、その代表的な例と言えるでしょう。
XPeng G9では、10.25インチのLCDメーターディスプレイに加え、中央には3中央には14.96インチの大型ディスプレイが2つ搭載されています。
3D HMIと物理世界を車両の画面に投影する機能のほか、AR技術と組み合わせた3Dナビゲーション表示などが実装されており、直感的に情報を把握できるだけでなく、車とのインタラクションも親しみやすくなっています。
一方、IM L7では、インテリア全体を「情報空間」と捉え、UIが空間演出の一部としてデザインされています。
車内のディスプレイは曲面化されており、時間帯やシーンに応じて色調や表示内容が変化。これにより、運転時は集中しやすく、休憩時にはリラックスできる環境が整えられています。
中国メーカーのHMIは、テクノロジーの採用スピードが非常に早く、ユーザー体験に対する柔軟な設計思想が特徴です。
3Dグラフィックスによる差別化は、今後ますます重要になると考えられます。
GM(GMC Hummer EV):オフロード向け3D UXの先鋭化
GMのGMCブランドから登場した「Hummer EV」では、オフロード走行に特化した3D UXが導入されています。
このモデルでは、車体の周囲を確認できるUltraVisionカメラと、地形をリアルタイムで可視化する3D HUDが連携しています。
特筆すべきは、3Dレンダリングによって地面の傾斜や障害物、タイヤの位置までが可視化される点です。これにより、ドライバーはまるでゲームのようなインターフェースで車両の動きを把握することができ、オフロードでも安心して操作が行えます。
こうした「ゲーム的なHMI」は、情報の視認性とエンターテインメント性を両立させる新たなアプローチとして注目されています。
機能性だけでなく、体験としてのドライブの価値を高める点で、3Dグラフィックスが重要な役割を果たしています。
HMIは“見る”から“感じる”へ
これまで見てきたように、3Dグラフィックスの導入によって、自動車のHMIは「情報を表示する装置」から「体験を創出するメディア」へと進化を遂げています。
この進化は、美しさや操作性の向上といった表面的な進歩にとどまらず、安全性の向上と技術的進展に根ざした必然的な変化とも言えます。
とくに近年、自動運転(AD)や高度な運転支援機能(ADAS)の実装が進んだことで、HMIには新たな役割が求められるようになりました。
車が部分的に運転を担うようになると、ドライバーは常にステアリングを握る必要がなくなり、そのぶん情報の受け取り方や車内での過ごし方にも新しい自由度が生まれます。
こうした環境下では、情報の「量」よりも「質」が重視されます。
例えば、3D表示によるナビゲーションや車両状態の可視化は、ドライバーが直感的に状況を把握できるようにし、運転中の判断を補助することで安全性の向上にも貢献しています。
さらに、インターフェースは単なる操作手段を超えて、快適さ・安心感・一体感を与える体験の核へと変わりつつあります。空間や光、音といった多感覚に訴えるHMIは、移動の質そのものを高め、車内時間の価値を再定義しています。
これからのHMIは、「見る」から「感じる」、そして「守る」へとその役割を拡張しながら、人とクルマの関係をより深く、豊かにしていくことでしょう。
シリコンスタジオでは、3Dグラフィックス技術を活用したHMIについて、Unreal Engine、Unity問わず、さまざまなニーズに対応した開発が可能です。デザインとエンジニアリングの両面から支援いたします。
理想的な3D HMIの実現や最適化に対して課題に直面している方は、お気軽にご相談ください。
■著者プロフィール:シリコンスタジオ編集部
自社開発による数々のミドルウェアを有し、CGの黎明期から今日に至るまでCG関連事業に取り組み、技術力(Technology)、表現力(Art)、発想力(Ideas)の研鑽を積み重ねてきたスペシャリスト集団。これら3つの力を高い次元で融合させ、CGが持つ可能性を最大限に発揮させられることを強みとしている。
DXコラムは、デジタルツインやメタバース、AIをはじめ産業界においてトレンドとなっているDX関連を中心としたさまざまなテーマを取り上げることにより、デジタル技術で業務の効率化を図ろうとする方々にとって役立つ学びや気付き、ノウハウなどを提供するキュレーション(情報まとめ)サイトです。