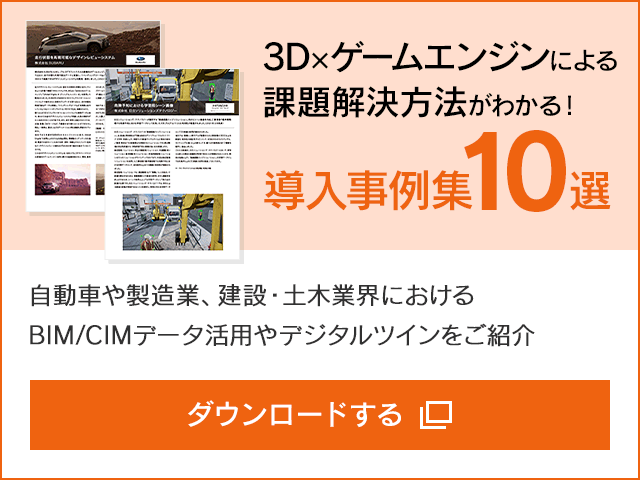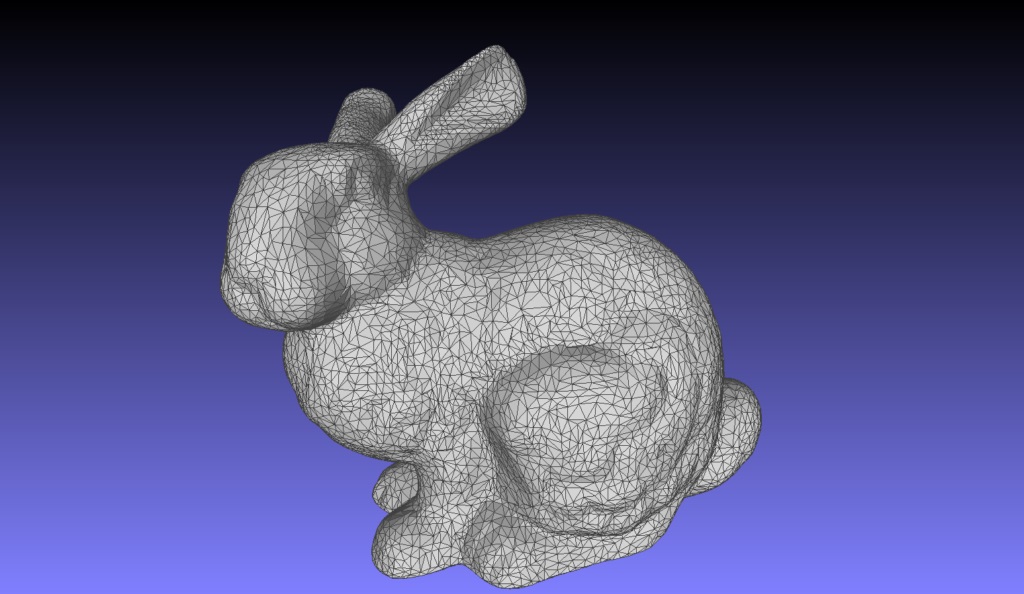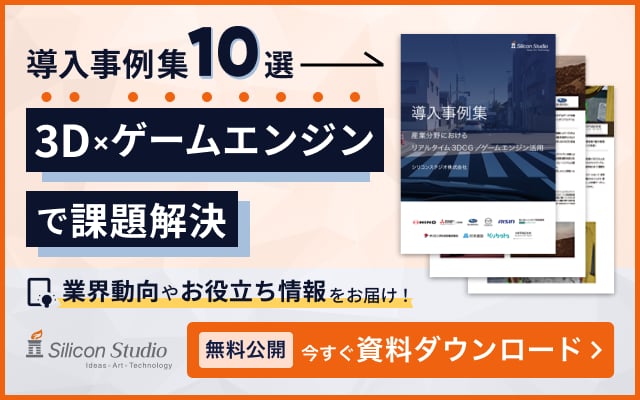- インフラ・情報通信
- その他
- 建築・土木
2025.09.19
防災×デジタルツイン&VR技術。災害対応を進化させるDXの実践と未来像
- 目次
- この記事を読むのにかかる時間:10分
世界の中でも日本は自然災害が非常に多い国である一方、行政の人手不足や高齢化、住民意識の低下が地域防災の課題です。災害発生時に適切な対応を取るためには訓練が不可欠であるのはもちろん、防災技術の革新が求められています。
そこで今注目されているのが、デジタルツインとVR(仮想現実)技術を活用した防災DXです。
本記事では、リアルな災害訓練やシミュレーションを実現する先端技術の活用法とその可能性についてご紹介します。
防災DXを支えるデジタルツインとVR技術の進化
ここでは、デジタルツイン技術とVRの基本概念や特徴を解説します。また、防災における利用の可能性として、災害時のシミュレーションや迅速な対応が可能になる点もご紹介します。
デジタルツインとは?災害対応での活用可能性
デジタルツインとは、現実世界の情報やデータをデジタル空間上に忠実に再現し、その空間でさまざまなデータ分析や将来予測などのシミュレーションを可能にする技術です。防災分野においては、都市や地域を3次元で仮想空間にモデル化し、人流・インフラデータ・気象情報などを統合、可視化することで、災害シミュレーションや被害予測、避難計画の策定、訓練など、多面的に活用されています。
例えば以下のような活用例が挙げられます。
- 3D都市モデルを活用したデジタルツイン空間で大規模地震や水害時の被害予測と最適な避難計画を立案
- ドローンで撮影したデータを元に災害現場の状況を可視化し、土砂崩れ現場の迅速な被害把握
- 災害発生時、リアルタイムデータ収集により、災害対応を迅速かつ的確に支援
VR技術の特徴と防災訓練での重要性
VR技術は、防災訓練において極めてリアルな体験を提供できることが最大の特徴です。仮想空間内で実際の災害状況(火災、地震、土砂災害など)を安全にシミュレーションし、避難行動や危険箇所の認識、煙の色に応じた避難方法まで、臨場感ある体験型訓練を実現することができます。
例えば、東京都では風水害の防災体験ができるVR動画「TOKYO VIRTUAL HAZARD -風水害-」を公開しています。風水害の脅威を疑似体験できるとともに、いざという時にとるべき行動なども学習できるものです。
動画は河川の氾濫、土砂災害、高潮による氾濫の3種類が用意されており、画面上をドラッグ(またはロングタップ)して見たい方向にスライドすることで、360度の自由視点で見ることができます。
〇TOKYO VIRTUAL HAZARD -風水害-
※映像を視聴することで精神的なストレスを感じることがあります。ご自身の判断で視聴くださいますようお願いいたします。
デジタルツイン・VRについての詳細は、以下の記事もご参照ください。
3Dデジタルツインで可視化する災害リスクと避難経路
災害時の状況把握や避難のためには、迅速かつ的確な判断が求められます。近年は、3Dデジタルツイン技術を用いた地形・気象シミュレーションや、避難経路策定とVRによる事前体験が注目されている状況です。ここでは、最新の取り組みや事例をもとに、それぞれ解説します。
災害リスクを“見える化”する地形・気象シミュレーション
3Dデジタルツインは、都市や地域の詳細な3Dモデルに地形や建物、インフラ、人口分布などの地域情報と災害関連データを重ね合わせ、台風・地震・津波などのリスクを直感的に可視化します。特に、浸水リスクや地形特性を考慮した洪水・津波のシミュレーションでは、現実空間の都市構造を忠実に再現した3D空間上で、被害想定を立体的に表示することが可能です。
見える化によって、以下のようなメリットが得られます。
- 行政や住民が災害リスクを即座に把握しやすくなり、防災意識や危機感を醸成できる
- シミュレーション結果をもとにした防災計画や備えの指針を具体的に立てやすくなる
- ハザードマップの3D空間重畳、AI分析によるピンポイントなリスク評価など、多様な活用のベースプラットフォームになる
防災教育や行政の意思決定、住民向けの啓発など幅広い分野で、こうした技術が活用されています。
最適な避難経路の策定とVRによる事前体験
3Dデジタルツインによる災害シミュレーションの発展形として、各地域や住民の状況に合わせた避難経路の最適化と、VRを活用した臨場感ある事前体験が注目されています。
実際の避難路を3D空間でシミュレーションし、浸水や瓦礫のリスク、滞留ポイント、人の流れなどを分析することで、安全で効率的な経路の選定が可能です。自治体・企業・教育機関などで導入が進み、参加者の防災行動力向上にもつながっています。
防災分野で実用化が進むデジタルツイン・VRの活用事例
ここでは、デジタルツインおよびVR技術を活用した災害対策や避難訓練シミュレーションの進化と、実際に活用されている事例をご紹介します。
VR技術の基本と防災分野への応用
VR技術は、ユーザーを仮想空間に没入させることで、現実さながらの災害状況や避難体験を提供します。防災分野では、被害現場を安全に、かつリアルに疑似体験できるため、防災意識の向上や実際の対応力アップにつながっています。
近年、学校・企業・自治体などで、災害リスク啓発や訓練、被災後の状況再現など幅広く活用されています。
中央大学のVR避難訓練の事例
中央大学は、南海トラフ巨大地震などで津波被害が想定される地域を想定し「バーチャル津波避難訓練」を開発しました。専用のVRゴーグルやセンサー付きシューズを用いて現地の町並みを再現したバーチャル空間内を徒歩で移動し、迫りくる津波からの現実的な避難ルート選択を体験できるシステムです。ゲームの仕組みを活用することで、参加者は没入感のある環境下で命を守るために「最適なルート」を自ら体験的に学べるのが特徴です。
実際に南海トラフ巨大地震で津波の被害が想定される地域の住民に体験してもらい、その結果を検証しながら開発を継続されています。
また、同大学は日本ライフセービング協会と協力し、溺水事故防止のための「溺れ体験VRコンテンツ」も開発しました。息を止めながら落水・沈下する場面をシミュレートし、水辺の安全教育にも現場で活用されています。
大阪・関西万博会場で避難誘導訓練
大規模イベントにおける応用例として、大阪・関西万博会場で実施されたVR訓練に注目が集まっています。2025年4月、大阪府警の会場警察隊が、夢洲(ゆめしま)の会場内パビリオンをVRで再現し、火災発生を想定した避難誘導訓練を行いました。
警察官たちは専用ゴーグルを装着し、仮想空間上の自分自身のアバターを操作しながら訓練を体験しました。再現された会場の各エリアで避難者の導線や誘導配置、声かけまでを仮想空間で確認することで、緊急時対応の精度と実践力を高めているのが特長です。府警の大規模現場訓練へのVR導入はこれが初であり、今後の防災運営体制強化に期待が寄せられています。
VR防災体験車(東京消防庁)
防災教育の現場におけるアウトリーチ型の例として、東京消防庁の「VR防災体験車」が挙げられます。「VR BOSAI」と名付けられた大型車両には、360度のCG映像と連動するMX4Dモーションシートを搭載しているのが特長です。参加者はVRゴーグルを着用し「地震編」「火災編」「風水害編」の臨場感あふれる災害疑似体験ができます。
座席が揺れたり、風や香りなど特殊効果もともなったりするため、臨場感のある災害体験が各地のイベントや学校・自治体行事で提供されています。防災教育における実践力や危機感の向上、防災訓練への関心喚起が狙いです。
3D浸水ハザードマップ(あいおいニッセイ同和損保)
![]()
デジタルツインの可視化事例として、あいおいニッセイ同和損保による「3D浸水ハザードマップ」が挙げられます。
国土交通省の3D都市モデル「PLATEAU(プラトー)」のデータなどをゲームエンジン「Unity」に取り込み、浸水リスクデータを3Dで重ね合わせて水害リスクを可視化しているのが特長です。災害発生時の特定条件での浸水表示、地図内の移動やズームなどの機能を備えており、浸水の深さや避難の必要性を実感することができます。
このほかにも、和歌山県田辺市での土砂災害対応など、全国的に導入が進んでいます。
自治体や住民は自分の街や自宅が具体的にどのような状況になるか体感できるため、リアリティのある避難計画策定や防災教育、リスク啓発に活用されています。防災・減災対策の現場で3D可視化とシミュレーションが加速中です。
防災におけるVR活用のメリットと導入時の課題
VR活用にはメリットがある一方、導入・運用時にはいくつかの課題が考えられるため注意が必要です。ここでは、防災におけるVR活用の効果について、実際どのように行動が変化するのか、効果と課題をご紹介します。
VR活用の主な効果・メリット
防災でのVR活用は、従来の手法を大きく進化させ、以下のようなメリットが得られます。
- 実際の災害時に近い現場の再現と体験性の高さ
- 記憶に残りやすい/防災意識の向上
- 能動的な学習による行動の変化
- 場所や時間を選ばない訓練/コスト削減
- 多様なシナリオやリスクの検証
VRの活用によって実際に災害現場が忠実に再現され、体験者はその場にいるかのような臨場感で避難経路の確認や災害対応行動を学べます。視覚・聴覚に加え、場合によっては触覚も刺激するため、参加者の印象や記憶への残り方が強く、防災意識が高まる効果が期待できるでしょう。
また、体験者自身が避難先や行動を選択し、その結果を振り返ることで、実際の災害時に瞬時の判断力や的確な行動につながるといった行動変容が見られるのもメリットです。オフィスや自宅など好きな場所・時間に体験でき、複数回繰り返すことも容易です。従来の実地訓練よりも手間やコストを抑えられます。
さらに夜間や大雨時など、多様な状況を自由に設定してシミュレーションできるため、従来型では難しいパターンでの体験、訓練も可能です。
VR活用における技術的・現実的な課題
VRの活用には、現場導入や運営面における、以下のような課題も指摘されています。
- 機器やコンテンツ準備の初期コスト
- 操作方法や没入感に個人差
- システムおよびシナリオの精度や汎用性
- 一部参加者の受動的姿勢による学習効果の変動
- ネットワークや端末環境など技術トラブル
VR機材や専用コンテンツの購入・準備にはコストがかかります。レンタルサービスなどで初期費用を抑える方法もありますが、継続的な費用対策が必要です。
また、VR機器の操作方法が苦手な人や、画面酔いによる体調不良を訴えるケースもあり、万人向けとは限らない点に注意が必要です。VR内の災害再現が現実と乖離していればリアリティや学習効果は下がります。したがって、施設ごとにシナリオやマップのカスタマイズも必要です。
テクノロジーに強い興味を持たない層の場合、受動的になりがちで、学びに違いが出る可能性も報告されています。遠隔実施時はネットワークの安定性や、VR端末のトラブルが訓練実施の妨げになる場合もあるため、事前の動作確認やサポート体制が不可欠です。
デジタルツイン×VRの連携による次世代防災システム
デジタルツインとVRを組み合わせることで、さらに効果的な防災システムが構築できる可能性があります。ここでは、2つの事例をご紹介します。
デジタルツインとVRの融合による新たな防災システム
デジタルツインとVRが組み合わさることで、現実の都市や施設の詳細な3Dモデル上で災害をシミュレーションし、現実では再現が難しい被害想定の避難訓練を、リアルかつ多角的に体験できる防災システムが登場しています。
代表的な事例として、NTTコミュニケーションズと東京理科大学による「市民参加型デジタル防災訓練」が挙げられます。本プロジェクトでは、国や自治体の都市空間オープンデータをもとに、建物や看板なども含めてリアルに3Dシミュレーションを実現しているのが特長です。市民はアバターとしてバーチャル空間で避難行動をし、その行動データを分析。災害時の避難行動の“見える化”と防災意識向上に活用されています。
![]()
また、建築設計大手とIT企業が共同開発したVR避難訓練ツールでは、デジタルツインで再現した建物内外をアバターで自由に避難体験可能。人数や混雑、時刻(昼夜)、さまざまな災害状況など多様なシチュエーションを再現し、避難経路や誘導灯配置の検証、サインの有効性ABテストなども行えるため、現実とリンクした防災対策に直結します。
未来の防災訓練と予防策
今後、デジタルツインとVRの高度な連携は、より実践的かつ効率的な防災訓練・予防策の主流になると見込まれています。
TOPPANが2025年3月から開始した新サービスでは、自治体の多様な災害・地域情報を3D空間と組み合わせて、被害想定や避難行動を住民属性ごとにAIがシナリオ生成しているのが特長です。行動ルールや地域計画とも連動し、自動で地域ごとの防災情報や訓練用CGを生成・活用できます。
これらの最先端事例から、デジタルツイン×VRによる防災は「状況再現」「避難体験」「データ分析」「個別最適化」など多様な側面から進化することでしょう。今後、防災教育や事業継続計画(BCP)、自治体・施設の訓練現場で一層の普及が期待されています。
防災技術の未来と市民参加による災害対応力の向上
ここでは、防災技術におけるVRやデジタルツイン技術の活用について今後の展望をご紹介します。
これからの防災技術の進化と期待
近年、防災分野ではAI・IoT・5G・クラウドなどの先進技術とデジタルツインやVRの融合によって、災害予測・避難シミュレーション・初動対応策の大幅な高度化が期待されています。
デジタルツイン技術では、都市や地域の詳細な3Dモデル×リアルタイム災害予測データの統合が進み、「被害予測モデルの多パターン化」「インフラごとの被災状況可視化」「個別避難誘導・被害情報の一元管理」などが現実になりつつあります。
今後はAIによる災害予測の精度向上、5Gによる即時多地点データ伝送、VR/ARによる個別対応型の避難訓練・教育提供といった多様な技術進化が進み、さらには「自律型対応システム」や「パーソナライズされた防災サービス」等の革新的サービスも登場が見込まれるでしょう。
エコシステムとしては、国や自治体・企業・住民横断でリアルタイムな災害情報共有/BCP連携の標準化も進みつつあります。
市民の意識改革と技術導入の課題
高度化する防災システムの実効性には、市民一人ひとりの災害対策行動や意識変革が不可欠です。ここまでで紹介した最新の研究・実証からも、以下のような課題が明らかになっています。
- 「参加型防災訓練」による意識向上とその限界
- 技術格差・インクルーシブな設計
- 地域性と協働推進の課題
- システム導入・継続運用のハードル
市民参加型VR訓練やデジタルツイン活用による避難シミュレーションは、防災意識や正しい避難行動の向上に寄与している一方、「参加者層の限定化」「体験訓練のマンネリ化」「訓練非参加層への啓発不足」などの問題も指摘されています。
新技術の理解や機材利用について年代やリテラシー格差が生まれやすく、高齢層・障がい者・子どもなど幅広い層へのアクセス保証が欠かせません。
また、防災活動への主体的参加には、地域の防災リーダー育成や多世代で学べる教育仕組み、体験型イベントなど新たな動機付け、地縁・コミュニティを核とした連携が有効とされています。デジタルツイン/VRの構築・導入コスト、ネットワークやプライバシー、セキュリティの課題、既存情報インフラとの統合・運用人材の確保も課題です。
防災DXに早めに取り組み、被害を抑制することが重要
日本では頻発する自然災害への対応力強化が課題となる中、デジタルツインとVRを活用した防災DXが進展しています。3D都市モデルや気象データなどを統合した災害リスクの可視化、最適避難経路のVR体験、自治体・大学・企業による市民参加型訓練や大規模イベントでの実証が拡大している状況です。臨場感ある訓練で防災意識を高めつつ、AI予測や多言語対応など技術は高度化しています。一方で機材コストや技術格差、参加層拡大など運用課題も残されているのが現状です。
シリコンスタジオでは、デジタルツインやVR技術を活用した防災・減災対策アプリケーションの開発実績から、お客様のニーズにあったご提案が可能です。導入のご検討に際してご不明な点、ご相談があれば、是非お気軽にお問い合わせください。
出典:国土交通省「災害リスク情報の3D可視化」
出典:国土交通省「屋内外をシームレスに繋ぐ避難訓練シミュレーション」
出典:国土交通省「1 防災分野のデジタル化施策」
出典:国土交通省 中部地方整備局「5. 防災意識改革と防災教育の推進」
出典:宮城県「みやぎ地域防災のアイディア集 08 住民参加・取組の促進」
出典:東京都防災ホームページ「TOKYO VIRTUAL HAZARD -風水害-」
■著者プロフィール:シリコンスタジオ編集部
自社開発による数々のミドルウェアを有し、CGの黎明期から今日に至るまでCG関連事業に取り組み、技術力(Technology)、表現力(Art)、発想力(Ideas)の研鑽を積み重ねてきたスペシャリスト集団。これら3つの力を高い次元で融合させ、CGが持つ可能性を最大限に発揮させられることを強みとしている。
DXコラムは、デジタルツインやメタバース、AIをはじめ産業界においてトレンドとなっているDX関連を中心としたさまざまなテーマを取り上げることにより、デジタル技術で業務の効率化を図ろうとする方々にとって役立つ学びや気付き、ノウハウなどを提供するキュレーション(情報まとめ)サイトです。