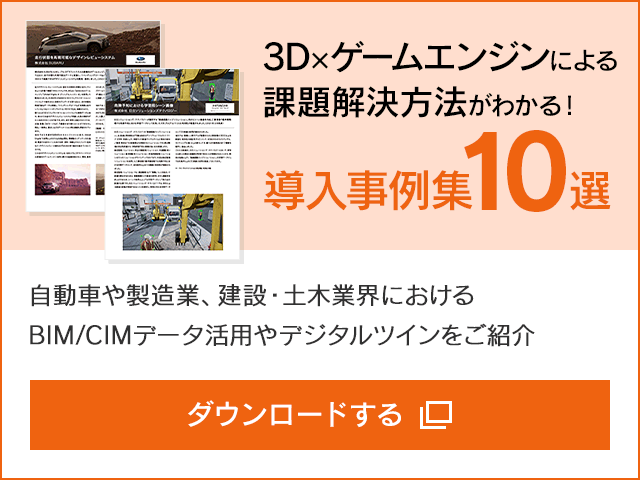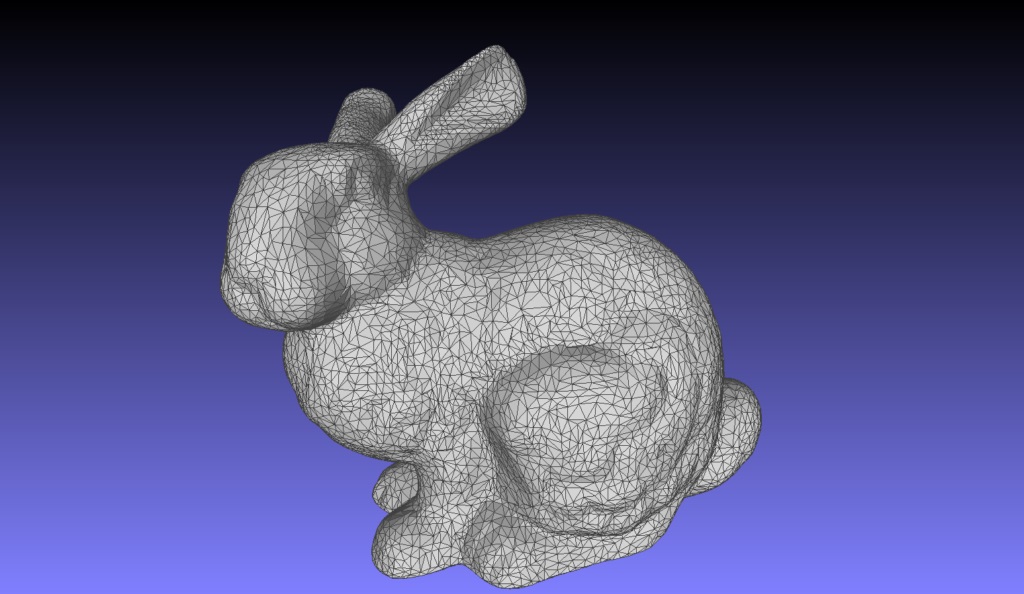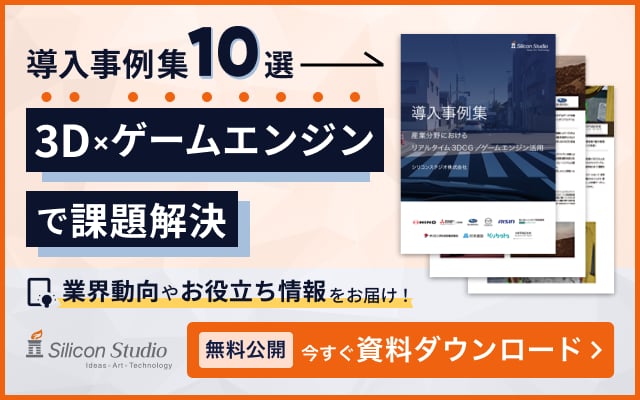- インフラ・情報通信
- その他
- 医療・福祉
- 宇宙・防衛
- 農林水産
2025.04.16
ムーンショット型研究開発制度とは?目標・取り組み・成果
- 目次
- この記事を読むのにかかる時間:10分
ムーンショット型研究開発制度は、日本発の破壊的イノベーション創出を目指す取り組みです。Society 5.0の実現に向け、従来技術の延長線上にない大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進します。
少子高齢化や環境問題など、困難な社会課題に対し、2050年までの達成を目指すさまざまな目標を設定しているのが特徴です。世界中の研究者の英知を結集し、人々を魅了する革新的な成果の創出に挑戦しています。
本記事ではムーンショット型研究開発制度について、概要、目標、開発プロジェクト、これまでの取り組みと今後の展望をご紹介します。
なお、Society 5.0の詳細は、以下の記事をご参照ください。
ムーンショット型研究開発制度とは
ムーンショット型研究開発制度とは、日本発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にはない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進する政府主導の制度です。本制度は、未来社会を展望し、困難ですが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題などを対象に、人々を魅了する野心的な目標(ムーンショット目標)を掲げて推進されます。ここでは、ムーンショット型研究開発制度の背景や特徴、研究推進体制を詳しく解説します。
制度の背景
ムーンショット型研究開発制度が創設された背景には、日本が直面する多くの困難な課題があります。例えば、少子高齢化の進行や大規模な自然災害への対応、さらには地球温暖化への対策などです。これらの課題解決に科学技術が果敢に挑戦し、未来社会の展望を切り拓いていくことが求められています。
海外に目を向けると、欧米や中国では、破壊的イノベーションの実現を目指し、日本とは比較にならない規模の投資を行い、リスクが高くても大きな成果が期待できる挑戦的な研究開発を積極的に推進している状況です。
制度の特徴
![]()
出典:内閣府「ムーンショット型研究開発制度とは/制度の特徴」
ムーンショット型研究開発制度では、目標ごとに複数のプロジェクトを統括するPD(プログラムディレクター)が任命され、その下で国内外の優れた研究者がPM(プロジェクトマネージャー)として採用されます。
また、研究全体を俯瞰できるポートフォリオを構築し、日本の基礎研究力を最大限に活用した挑戦的な研究開発を積極的に推進する点が特徴です。ポートフォリオは、ステージゲートを設けて柔軟に見直し、将来的な社会実装を視野に入れながら派生的な研究成果のスピンアウトを促進します。
さらに、失敗を許容しつつ挑戦的な研究を推進するとともに、データ基盤を活用した最先端の研究支援システムの構築も、本制度の大きな特徴といえるでしょう。
研究推進体制
ムーンショット型研究開発制度の研究推進体制は、以下のとおりです。
- 総合科学技術とイノベーション会議(CSTI)、健康・医療戦略推進本部
- ムーンショット型研究開発制度に係る戦略推進会議
- 研究推進法人を所管する関係府省
- 研究推進法人(JST、NEDO、BRAIN、AMED)
総合科学技術とイノベーション会議(CSTI)と健康・医療戦略推進本部は、外部の有識者などの意見を踏まえ、ムーンショット目標を決定する会議です。
一方、ムーンショット型研究開発制度に関する戦略推進会議は、研究開発の戦略的推進や成果の実用化の加速、さらに関係府省や研究推進法人間の効果的な連携・調整を目的として設置されています。産業界、研究者、関係府省などで構成され、毎年度、研究推進法人から進捗の報告を受け、全体俯瞰的な観点から、プロジェクトの構成の考え方、資金配分の方針等について助言を行う役割です。
さらに内閣府や文部科学省、経済産業省、農林水産省、厚生労働省が、挑戦的研究開発を推進すべき分野・領域などを定めた研究開発構想を策定します。戦略推進会議での議論を基に、研究開発を戦略的かつ統合的に推進する役割を担っています。
また、JST、NEDO、BRAIN、AMEDといった研究推進法人は、それぞれ特定のムーンショット目標の達成に向けた研究開発を実施する担当です。PDの任命、PMの公募・採択、研究開発の実施およびそれに付随する調査・分析機能等を含む研究開発推進体制の構築、研究開発の進捗管理を行います。
ムーンショット型研究開発制度の目標
![]()
ムーンショット型研究開発制度の推進により、具体的にどのようなことを実現しようとしているのでしょうか。ここでは、ムーンショット型研究開発制度の目標に関して解説します。
目標設定の過程
ムーンショット型研究開発制度における目標設定は、以下のように段階的、かつ慎重に行われました。
1.ビジョナリー会議の設立
有識者で構成されるビジョナリー会議が設立され、未来社会を展望し、顕在化が予想される国内外の社会課題を解決する観点から目標を検討しました。
2.意見聴取と提案受付
ビジョナリー会議は4回にわたる会合を実施し、産業界からの意見を収集するとともに、一般の方々(約1,800件)や関係府省からの提案も受け付けました。
3.目標案の策定
ビジョナリー会議では25の目標例を提案され、これを基に6つの目標案が策定されました。
4.目標の決定
総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)が、最終的にムーンショット目標を決定しました。
5.追加目標の設定
当初の6つの目標に加え、その後の会議で追加の目標が設定され、現在は10個のムーンショット目標が掲げられています。
設定された目標の概要
ムーンショット型研究開発制度では、以下の目標が設定されています。
- 目標1:2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現
- 目標2:2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現
- 目標3:2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現
- 目標4:2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現
- 目標5:2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出
- 目標6:2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現
- 目標7:2040年までに、主要な疾患を予防・克服し100歳まで健康不安なく人生を楽しむためのサステイナブルな医療・介護システムを実現
- 目標8:2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現
- 目標9:2050年までに、こころの安らぎや活力を増大することで、精神的に豊かで躍動的な社会を実現
- 目標10:2050年までに、フュージョンエネルギーの多面的な活用により、地球環境と調和し、資源制約から解き放たれた活力ある社会を実現
これらの目標は、社会、環境、経済の3つの領域に関連しており、人々の幸福(Human Well-being)の実現を目指しているのが特徴です。各目標は相互に関連し、総合的に未来社会の課題解決を目指す構造となっています。
例えば、目標1と3はロボットやAI技術の発展を通じて人間の能力拡張を目指し、目標2、7、9は健康や精神面での課題解決を目指すなど、目標間で相乗効果が期待されています。
主なムーンショット型研究開発プロジェクト
ムーンショット型研究開発制度における、主なムーンショット型研究開発プロジェクトは以下のとおりです。
- 未知未踏領域における拠点建築のための集団共有知能をもつ進化型ロボット群
- 環境再生と持続可能な資源循環
- 農業における土壌微生物活用
- 睡眠と冬眠の研究
これらのプロジェクトは、日本の科学技術イノベーションを推進し、未来社会の課題解決に向けた重要な取り組みです。それぞれの内容を確認しておきましょう。
未知未踏領域における拠点建築のための集団共有知能をもつ進化型ロボット群
本プロジェクトの目的は、月面溶岩チューブ内での探査や拠点建築を行う進化型ロボット群システムの構築です。中央大学の國井康晴教授がプロジェクトマネージャーを務め、単純な機能をもつ小型ロボットが群を形成し、集団として知能を発揮する仕組みの研究開発を行っています。(「目標3:2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」に該当)
このプロジェクトで開発される技術は、ロボット群全体で共通した機能の更新・拡張と、新規ロボットの追加による群の進化を実現します。また、多数のロボットが協力して活動拠点コンテナを搬送し、コンテナが自動展開して活動拠点となる仕組みを開発することが可能です。
月面での活動だけでなく、地球上での資源探査や災害対応などへの応用可能性も視野に入れられています。
環境再生と持続可能な資源循環
環境再生と持続可能な資源循環は、2050年までに実現を目指す重要なムーンショット目標の1つです。地球温暖化問題(Cool Earth)と環境汚染問題(Clean Earth)の解決を目指しています。(「目標4:2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」に該当)
本プロジェクトの主な取り組みは、温室効果ガスの回収・資源転換・無害化技術の開発、窒素化合物の循環技術の創出、そして海洋生分解性プラスチックの開発などです。資源の完全循環と資源要求の劇的削減を実現し、持続可能な社会の構築を目指しています。
農業における土壌微生物活用
土壌微生物の活用は、持続可能な農業実践において重要な役割を果たしています。土壌微生物は、土壌の栄養バランスを保ち、病原菌の抑制、連作障害の防止、そして柔らかい土の生成に貢献することが特徴です。(「目標5:2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」に該当)
土壌微生物を増やす方法としては、堆肥の使用、米ぬかの散布、計画的な雑草の刈り取り、そして輪作などが挙げられます。これらを適切に組み合わせることで、農薬に頼らない作物栽培や、より健康的で生産性の高い土壌環境を作り出すことが可能です。
睡眠と冬眠の研究
睡眠と冬眠の研究は、生物学的な「眠り」の謎に挑む重要なプロジェクトです。(「目標7:2040年までに、主要な疾患を予防・克服し100歳まで健康不安なく人生を楽しむためのサステイナブルな医療・介護システムを実現」に該当)
2020年6月に発表された研究では、マウスの脳の特定の神経細胞群(Q神経)を刺激することで、冬眠様状態を誘導できることが明らかになりました。この発見は、冬眠しない動物種でも人工的に冬眠様状態を引き起こせる可能性を示唆しており、人間への応用も期待されています。
また、レム睡眠の重要性も研究されており、大脳皮質における物質交換にレム睡眠が重要な役割を果たしている可能性が示唆されている点もポイントです。睡眠障害や認知症など、健康問題に対する新たな治療法の開発につながる可能性があります。
ムーンショット型研究開発のこれまでの取り組みと成果
ここからは、ムーンショット型研究開発のこれまでの取り組みと成果をご紹介します。
主要プロジェクトの進捗状況
前述のとおり、ムーンショット型研究開発事業では、現在10個の目標に向けて多数のプロジェクトが進行しています。例えば目標1では、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会の実現を目指し、サイバネティックアバター技術※の開発が進んでいます。目標3では、AIとロボットの共進化を目指し、自律的に判断・行動し人と共生するAIロボットの開発が進められている状況です。一部のプロジェクトでは実験室レベルでの概念実証が行われ、実用化に向けた重要な一歩を踏み出しています。
※サイバネティックアバター技術:仮想空間にある自分の分身(アバター)を操作することで、現実世界に価値を創出する技術のこと
また目標4では、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環の実現を目指し、大気中からのCO2直接回収(DAC)技術の開発が進みました。実機サイズのCO2固体吸収材の評価に着手するなど、具体的な成果が出始めており、環境問題解決への貢献が期待されています。
社会実装に向けた取り組み
ムーンショット型研究開発制度では、研究成果の社会実装を重視しています。将来的な社会実装を見据え、研究開発の早い段階から産業界を巻き込んだオープン・クローズ戦略を検討されてきました。
また、派生的な研究成果のスピンアウトを積極的に奨励し、社会実装の加速を図っています。多様な人々との対話の場を設け、倫理的・法制度的・社会的課題について人文社会科学の知見も取り入れながら検討を進めている状況です。例えば、トヨタ自動車が静岡県裾野市で進める「Woven City」プロジェクトでは、自動運転技術やロボット、AI技術の実証実験を行う実験都市の建設が始まっており、ムーンショット型研究開発の成果の実用化に向けた取り組みが進んでいます。
国際協力と標準化への貢献
ムーンショット型研究開発制度は、国際連携を重視し、グローバルな課題解決に貢献することが目的です。海外の研究機関・研究者も参画可能な枠組みを設け、国際的な英知の結集を図っています。具体的な連携事例として、石黒浩教授(大阪大学)のプロジェクトがUAEのドバイ未来財団と連携するなど、各目標で国際的な協力関係が構築されました。
一方、研究成果の国際標準化に向けた取り組みも進められており、特に量子コンピュータや環境技術の分野で日本の技術の国際的な位置づけを高めることが期待されています。
ムーンショット型研究開発の今後の展望と課題
今後、ムーンショット型研究開発制度は、どのように推進されていくのでしょうか。ここでは、ムーンショット型研究開発の今後の展望と課題をご紹介します。
今後の展望
2025年3月に多くのプロジェクトの初期研究開発期間が終了するため、この時点で重要な進捗評価が行われます。この評価結果に基づき、プロジェクトの継続や方向性の調整が行われる可能性があるでしょう。
また、既存のプロジェクトの進捗状況や社会のニーズの変化に応じて、新たな研究プロジェクトが開始される可能性もあります。ムーンショット目標の達成に向けた取り組みがさらに強化されることが期待されるでしょう。
ムーンショット型研究開発制度では、世界中から研究者の英知を結集することを目指しています。今後、海外の研究機関との連携をさらに強化し、グローバルな視点での研究開発を推進することが重要です。
課題
ムーンショット型研究開発制度は2050年という長期的な目標に向けて、技術的な実現可能性を常に評価し、必要に応じて目標や研究アプローチを柔軟に調整しなくてはなりません。ムーンショット目標を達成するためには、異なる分野の研究者や技術の融合が不可欠です。分野を超えた効果的な協力体制の構築が課題となります。
また、革新的な研究成果を実際の社会課題の解決につなげるためには、産業界との連携や規制の整備など、社会実装に向けた取り組みも欠かせません。研究開発の早い段階から社会実装を見据えた戦略が必要です。
破壊的イノベーションを創出することが期待されている
ムーンショット型研究開発制度は、破壊的イノベーション創出を目指し、2050年までに少子高齢化や環境問題などの社会課題解決に挑む日本発の取り組みです。Society 5.0実現を目標に、AIやロボット、量子コンピュータ、環境再生技術など10の分野で研究を推進しています。失敗を許容しつつ、研究成果の社会実装や国際協力を重視しているのが特徴です。将来的には新たなプロジェクトの展開や産業界との連携強化が期待され、分野を超えた協力体制の構築が課題となっています。
シリコンスタジオでは、ムーンショット型研究開発を支援する3Dグラフィックス技術を数多く提供しております。是非、シリコンスタジオにご相談ください。
出典:文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤課「ムーンショット型研究開発制度について」
出典:文部科学省「第4章 イノベーション創出に向けた「知」の社会実装」
出典:経済産業省「ムーンショット目標4」
出典:総務省「国立研究開発法人情報通信研究機構/令和4年度の業務実績に関する項目別自己評価書」
出典:内閣府「ムーンショット型研究開発制度」
出典:内閣府「国際連携」
出典:内閣府「ムーンショット型研究開発制度の基本的考え方について」
出典:内閣府「ムーンショット型研究開発制度とは」
出典:内閣府「ムーンショット型研究開発制度の運用・評価指針(ムーンショット目標1~6、8~10)」
出典:内閣府「ムーンショット目標4 2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」
■著者プロフィール:シリコンスタジオ編集部
自社開発による数々のミドルウェアを有し、CGの黎明期から今日に至るまでCG関連事業に取り組み、技術力(Technology)、表現力(Art)、発想力(Ideas)の研鑽を積み重ねてきたスペシャリスト集団。これら3つの力を高い次元で融合させ、CGが持つ可能性を最大限に発揮させられることを強みとしている。
DXコラムは、デジタルツインやメタバース、AIをはじめ産業界においてトレンドとなっているDX関連を中心としたさまざまなテーマを取り上げることにより、デジタル技術で業務の効率化を図ろうとする方々にとって役立つ学びや気付き、ノウハウなどを提供するキュレーション(情報まとめ)サイトです。